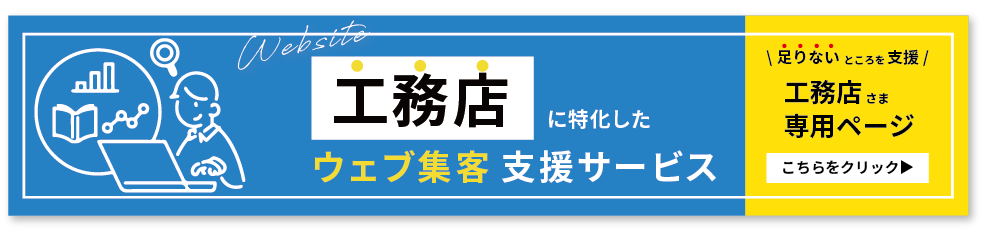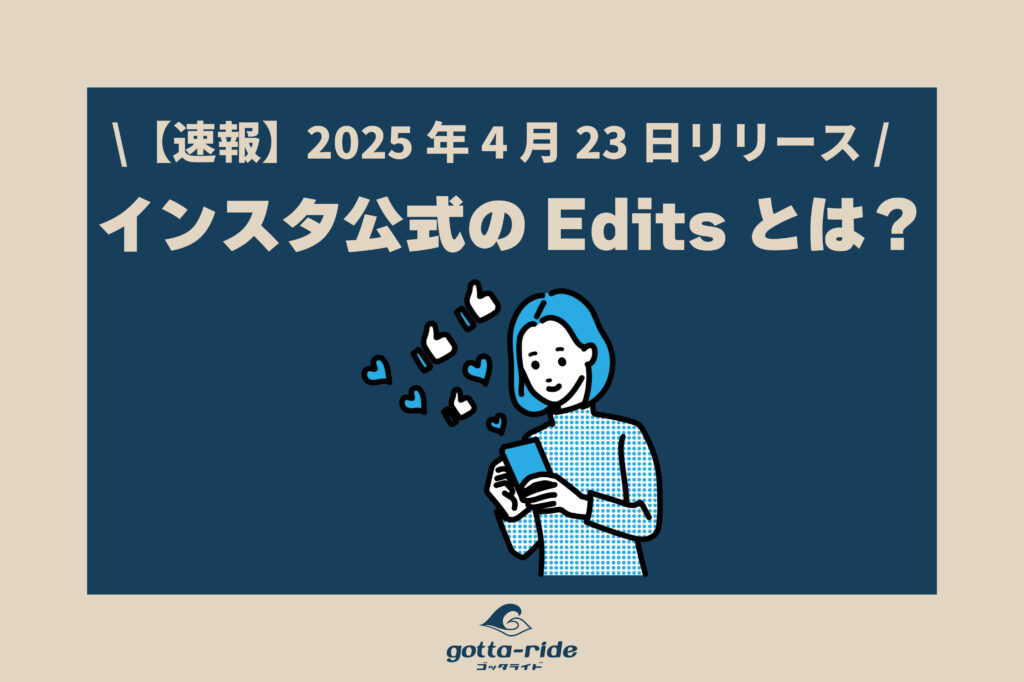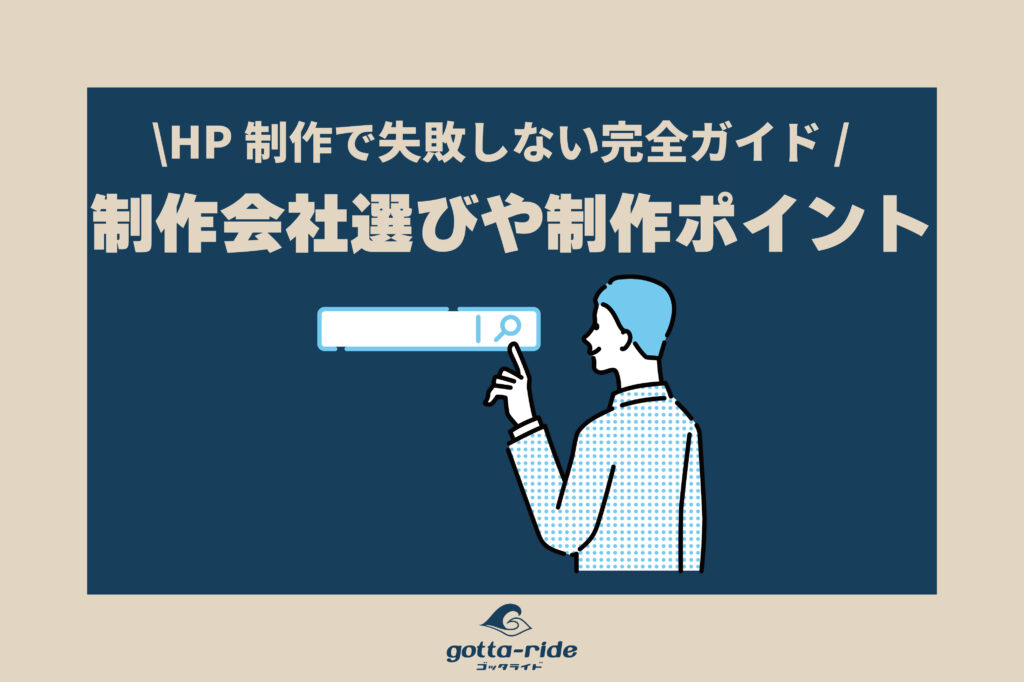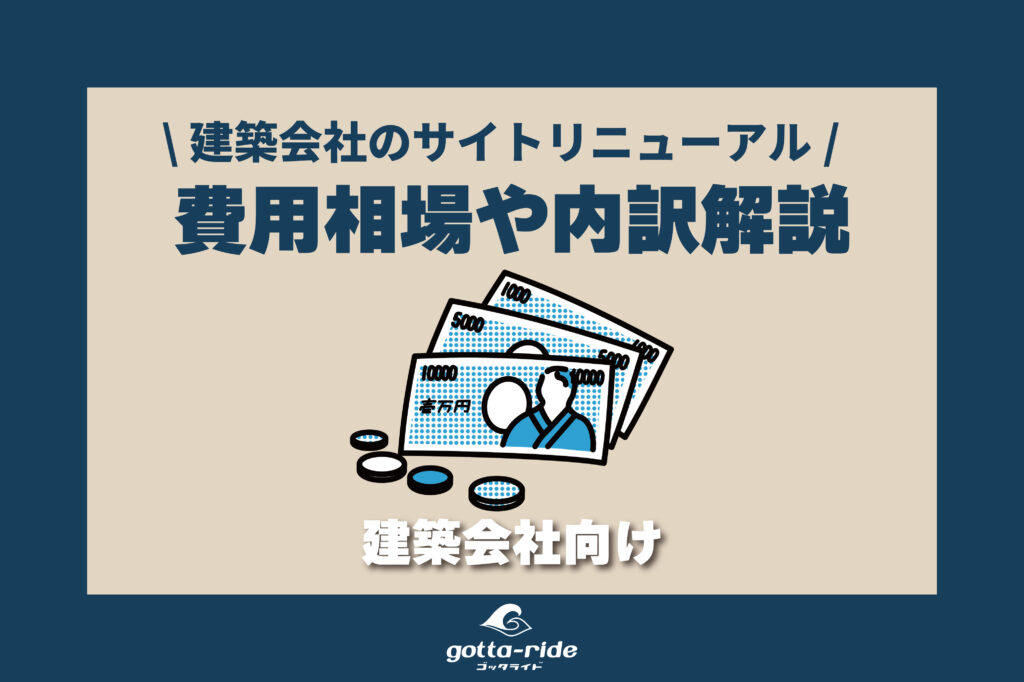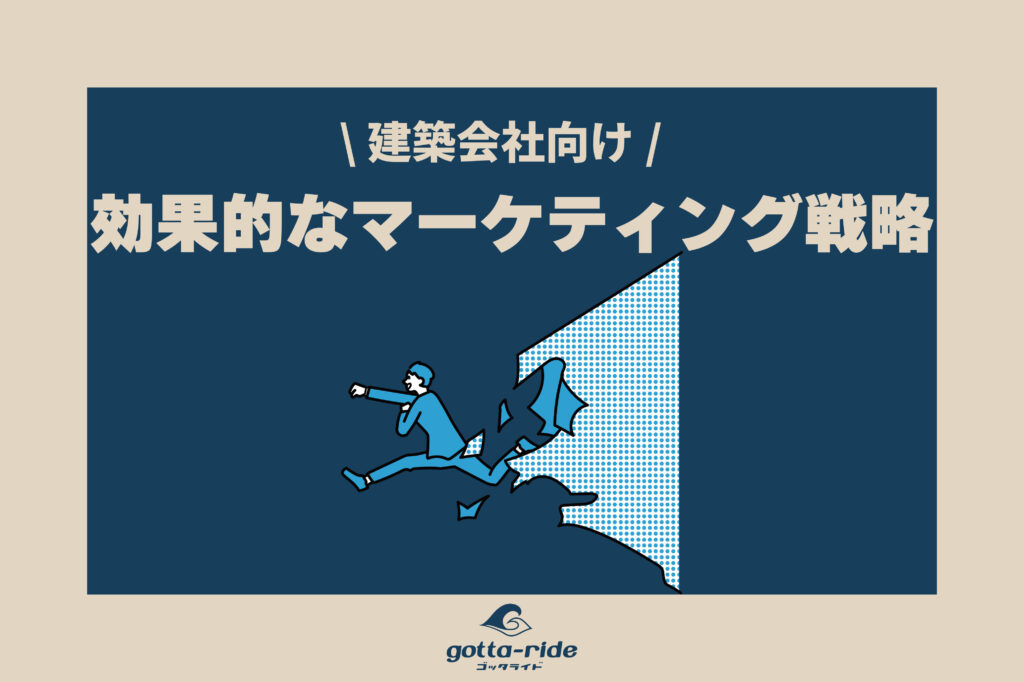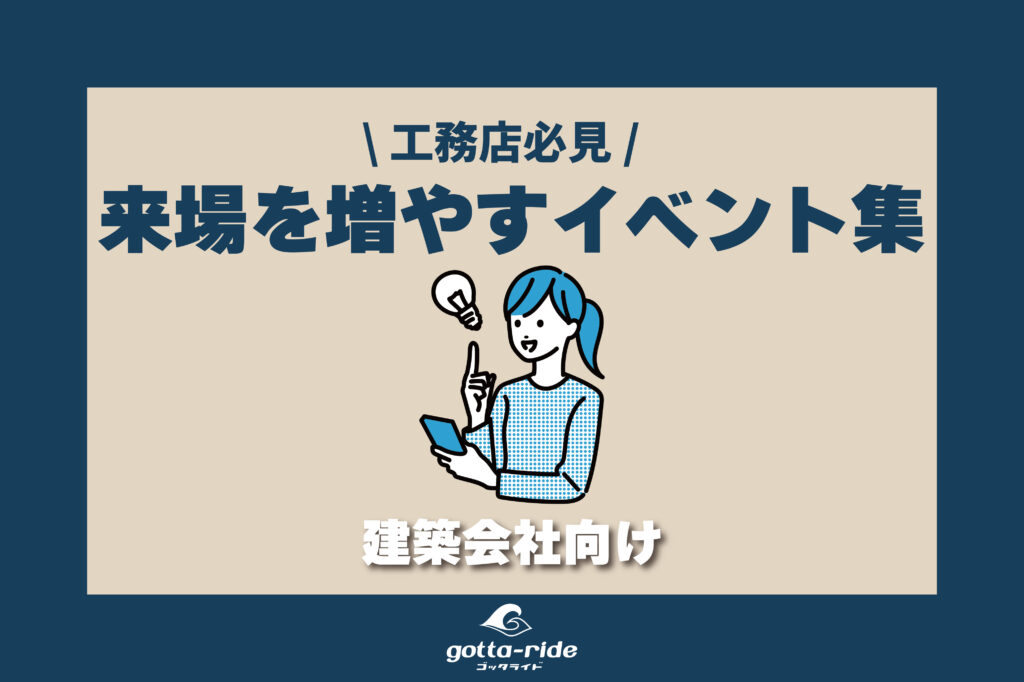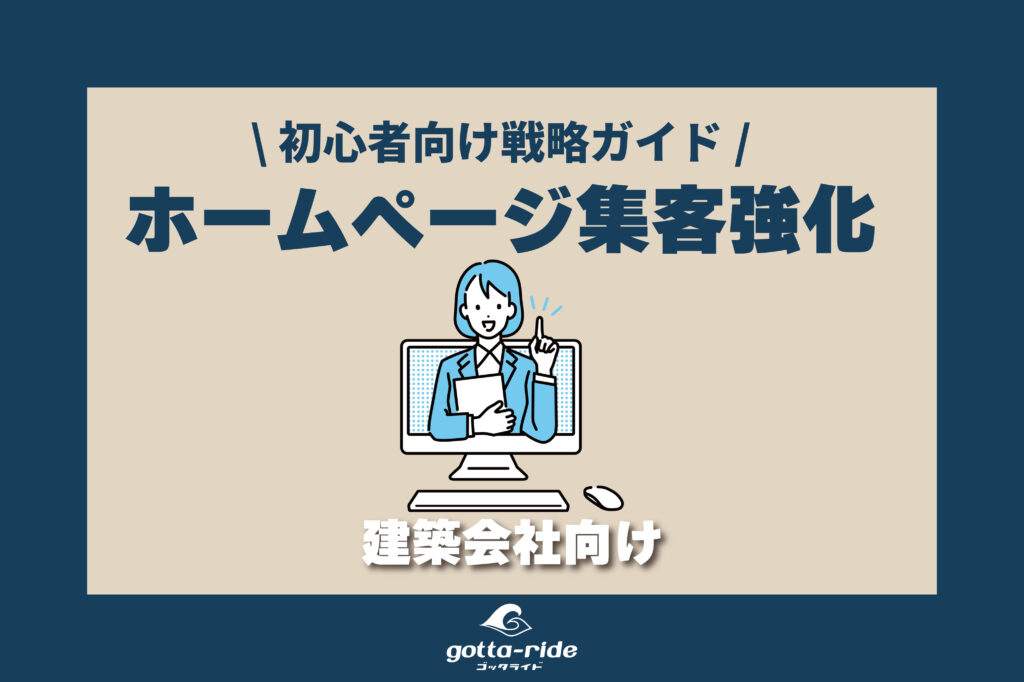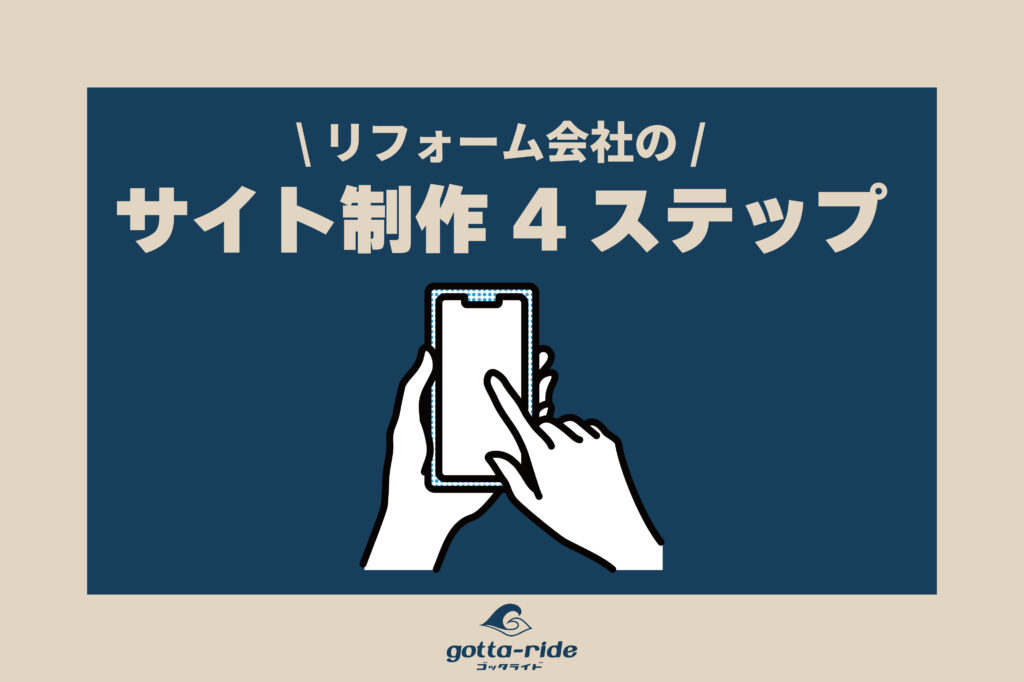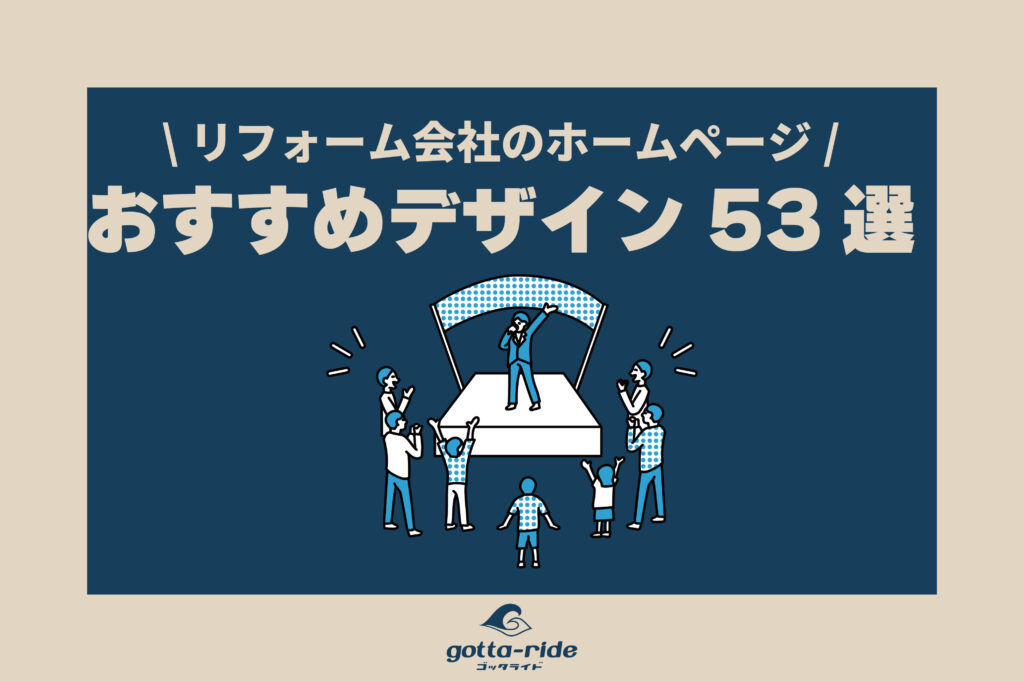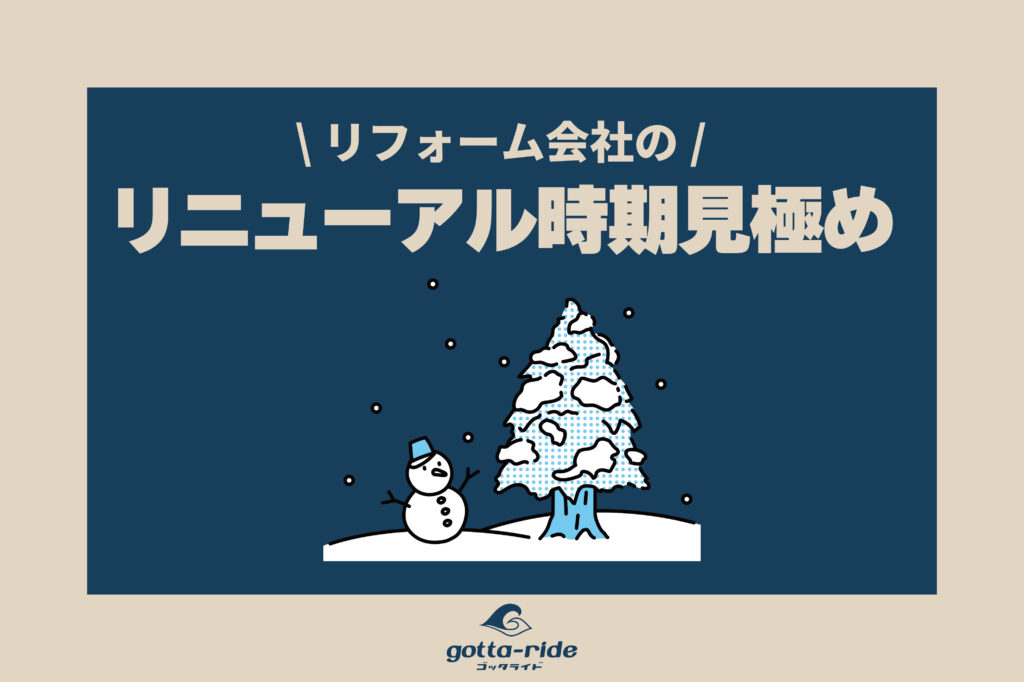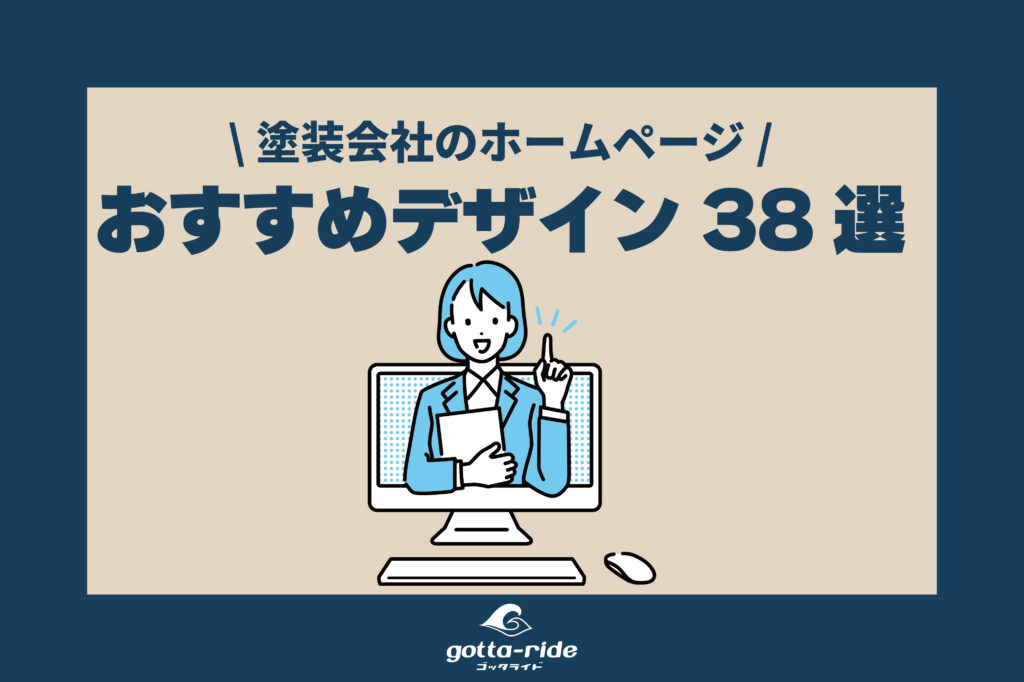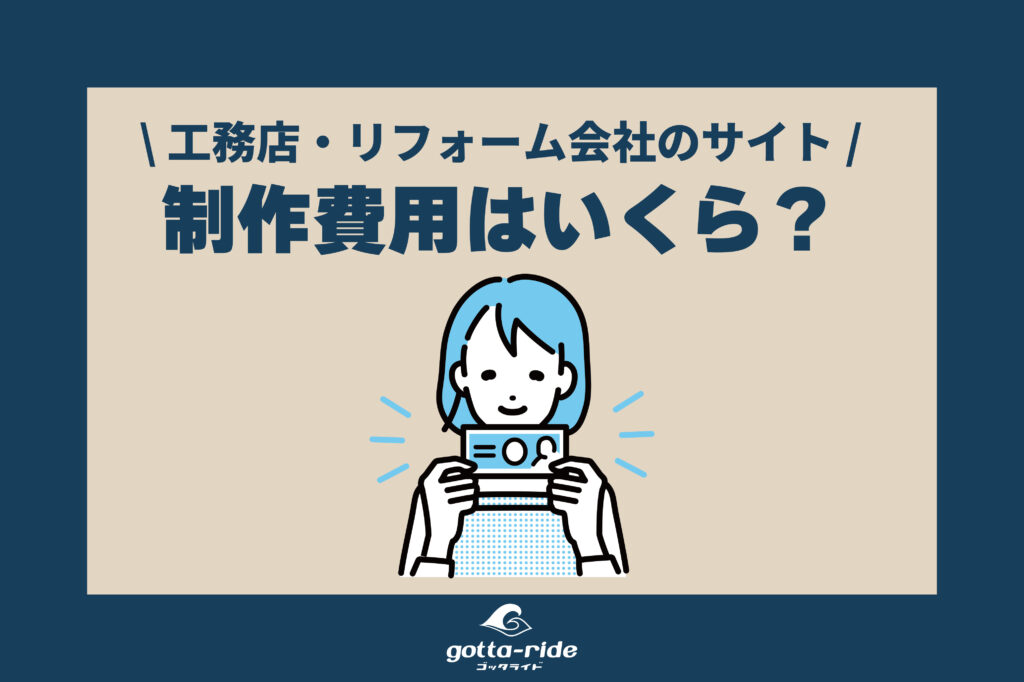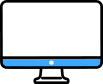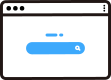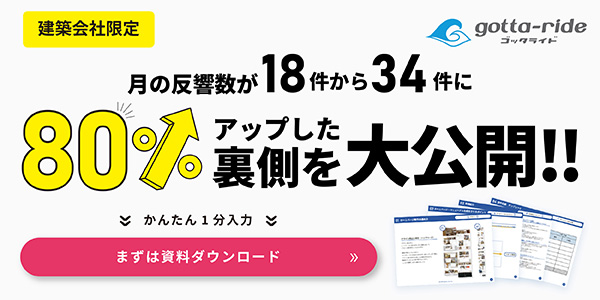SNS運用・SNS集客
ホームページから反響が出ない原因は構成かも?建築業界向けwebサイト改善ポイントを徹底解説!
公開日:2025/04/24
最終更新日:2025/04/24
こんにちは。工務店、リフォーム会社のホームページ集客支援のゴッタライドです。
「ホームページはあるけど、思ったほど問い合わせが来ない…」
「施工事例は充実しているのに、見てもらえていない気がする」
そんなお悩みをお持ちの建築会社の方は少なくありません。
多くの工務店やリフォーム会社、塗装会社がウェブ集客に力を入れる中で、「かっこいいデザイン」や「写真映え」だけを重視したホームページが増えてきました。多くの建築関連企業では、ホームページを“名刺代わり”にとどめてしまっているケースが見受けられますが、それでは十分な反響は期待できません。また、ホームページの見た目だけでは反響獲得の成果に結びつかないのが現実です。
反響獲得の成果を出すホームページに必要なのは、ユーザーの行動を導く「構成」と「導線設計(デザイン)」です。本記事では、建築業界に特化したホームページ制作を行ってきた私たちゴッタライドの視点から、効果的な構成とデザインの考え方を具体的に解説します。
今あるサイトを改善したい方にも、新規制作を検討している方にも役立つ内容です。ぜひ最後までご覧ください。

ホームページの構成とは
ホームページの「構成」とは、サイト全体や各ページにおける情報の配置や流れを指します。建築会社のホームページでは、施工事例やサービス紹介、問い合わせなど、訪問者のニーズに合わせた情報を整理し、必要な場所に配置することが必要不可欠です。
見た目のデザインが美しくても、情報が探しづらければユーザーの理解や行動につながりません。ホームページは単なるデザインだけでなく、どの情報をどこに置くかという「構成」が、訪問者の理解度や行動に大きく影響します。
ホームページの構成の重要性
構成がしっかりしていると、ユーザーは迷うことなく目的の情報にたどり着きやすくなります。その結果、問い合わせや資料請求といった「次のアクション」へと導きやすくなります。
逆にホームページの構成が悪いと、せっかく集めたアクセスが離脱してしまう原因になります。アクセスが成果につながらないケースも少なくありません。ホームページの構成は、サイトのデザインや文章と並んで、サイトの成果を左右する大きな要素であり、「反響を得られるサイト」をつくるための基盤となります。
ユーザー体験とSEOへの影響
ユーザーがスムーズに情報を探せるホームページの構成は、サイトの滞在時間や回遊率を高め、検索エンジンからの評価向上にもつながります。Googleをはじめとする検索エンジンは、ユーザー体験を重視しており、分かりやすいナビゲーションや論理的なページ構成はSEOでも高く評価しています。見た目だけではなく、「使いやすさ」を意識した構成設計が、検索結果にも良い影響を与えるのです。
リフォーム会社に特化したウェブ集客支援サービスのページはこちら
サイト全体の構成を考える
ホームページの制作やリニューアルを行う前に、まずサイト全体の役割やゴールを明確にすることが重要です。「誰に」「何を」「どの順序で」伝えるのかを整理することで、訪問者にとって自然な情報導線を設計できます。
たとえば、住宅検討中のユーザーに向けては、まずサービス内容を伝え、施工事例で安心感を与え、最後に問い合わせへ誘導するといったストーリー設計が効果的です。また、広告経由のユーザーだと、イベントページからイベント内容を伝え、施工事例で安心感を与え、再度イベントページに戻り予約をするという設計も考えられます。
サイト構成のポイント
サイト構成を考える際には、見た目のデザインや自社の伝えたいことだけに注目するのではなく、ユーザーが「どのように情報を探し、どのように行動するか」を基準に設計することが何より大切です。
以下の3つのポイントは、建築会社のホームページを構成するうえで特に重要な観点です。
サイト構成のポイント①ユーザー視点での設計
構成設計で最も大切なのは、自社目線ではなく「ユーザー目線」で考えることです。
たとえば、「このサービスを知ってほしい」「会社の想いを伝えたい」といった気持ちは自然ですが、それだけでは不十分です。
ユーザーは何を求めてサイトに訪れているのか?
どの情報を、どの順番で知りたいのか?
それに応える構成でなければ、たとえどれだけ素敵なデザインでも、成果にはつながりません。また、スマートフォンでの閲覧が主流となっている現在では、小さな画面でも直感的に操作できる導線設計が必須です。メニューのタップしやすさ、スクロール前提の情報配置、CTAの視認性など、「モバイルでのユーザー体験」にも意識を向けましょう。
サイト構成のポイント②情報の明確なカテゴライズ
ユーザーが必要な情報に迷わずアクセスできるように、情報をしっかり分類(カテゴライズ)して構成することが重要です。
たとえば、「サービス紹介」「施工事例」「料金」「よくある質問」といったカテゴリに分けてメニューを構成し、それぞれの中で情報を整理すると、ユーザーは自分が求めている情報にスムーズにたどり着けます。このカテゴライズが不明確だと、ユーザーは「どこを見ればいいのかわからない」と感じて離脱してしまう可能性が高まります。見出しやメニューはシンプルかつ直感的に、業界用語よりも「ユーザーが普段使う言葉」で表記することが大切です。
サイト構成のポイント③階層を深くしない
サイトの階層が深すぎると、ユーザーは目的の情報にたどり着くまでに何度もクリックやタップをしなければならず、ストレスを感じて離脱してしまうことがあります。理想は、トップページから2〜3クリック以内で、主要な情報にアクセスできる構造にすることです。
施工メニュー、料金案内、施工事例、お客様の声など、ユーザーが特に関心を持ちやすいコンテンツは、できるだけ浅い階層で表示できるようにしましょう。また、検索エンジン(SEO)の評価においても、浅く整理された構造は好まれます。クローラーがページを巡回しやすくなり、サイト全体の評価向上にもつながるため、構成設計の段階から意識しておくべきポイントです。
サイトマップ作成のメリット
サイト全体の構成を考える最初のステップとして、サイトマップの作成があります。サイトマップとは、ホームページの全体構成を図にした「設計図」のようなものです。これを作ることで、全体の情報整理がしやすくなり、漏れや重複も防げます。
ゴッタライドでは、初回打ち合わせの段階でこのサイトマップを共有し、どのような構造のサイトにするかをクライアントと一緒に確認します。図として可視化することで、社内や外注先との認識共有もスムーズに行えるのが大きなメリットです。
効果的なサイトマップの作成手順
ホームページ制作やリニューアルの成功は、構成設計=「設計図づくり」から始まります。建築会社のホームページでは、トップページだけでなく、サービス紹介、施工事例、お客様の声、よくある質問、問い合わせページなど、複数のページが連動してユーザー体験をつくります。そのため、全体の情報構造を俯瞰できるサイトマップを事前に設計しておくことで、情報の漏れや重複を防ぎ、ユーザーにとってわかりやすい導線設計が可能になります。ここでは、効果的なサイトマップを作るための3つのステップをご紹介します。
サイトマップの作成手順①目的の設定
最初に明確にすべきなのは、ホームページの「目的」です。ホームページの目的(集客/採用/ブランド認知など)を明確にします。目的がぶれると、構成全体も曖昧になります。
- 見込み客からの問い合わせを増やしたい(=集客)
- 採用応募者に自社の魅力を伝えたい(=採用強化)
- 地域での認知度を高めたい(=ブランド認知)
目的があいまいなまま構成を決めてしまうと、「伝えたいことが伝わらない」「ユーザーの行動が起きない」といった失敗につながります。目的が明確になれば、「どの情報を載せるべきか」「どのページが必要か」「何を優先的に見せるべきか」も自然と見えてきます。
サイトマップの作成手順②ページのリストアップと分類
目的が定まったら、次は必要なページをすべて洗い出してリスト化します。必要なページ(会社概要、サービス紹介、施工事例など)を洗い出し、グルーピングしていきます。
たとえば
- 会社概要
- スタッフ紹介
- サービス紹介(リフォーム/注文住宅/外壁塗装など)
- 施工事例
- お客様の声
- よくある質問(FAQ)
- お知らせ/ブログ
- お問い合わせ
洗い出した後は、情報のジャンルごとにグループ化(カテゴライズ)していきます。この段階では「カテゴリーメニューに入れるもの」「下層に配置すべきもの」などを整理することが重要です。こうした分類を丁寧に行うことで、ユーザーが必要な情報にたどり着きやすいサイト構成の基礎ができます。
サイトマップの作成手順③階層構造の決定
最後に、ページ同士の階層構造(リンク構造)を決めていきます。理想は、ユーザーがトップページから2〜3クリック以内で、目的のページにたどり着ける構成です。階層が深すぎると、訪問者が途中で迷って離脱するリスクが高まります。また、検索エンジンも浅い階層構造を好む傾向があり、SEOの観点からも「3階層以内」が基本とされています。
例えば
|
トップページ ├ サービス紹介 │ ├ 外壁塗装 │ ├ 水回りリフォーム ├ 施工事例 ├ お客様の声 ├ よくある質問 ├ お問い合わせ |
このように整理されたサイトマップを設計することで、制作段階でも迷いが少なく、ユーザーにとっても直感的に使いやすいホームページが実現できます。
さらに進んだステップとして、「どのページから何ページへ遷移するか(導線設計)」や「スマホでの動線検証」もありますが、まずはこの基本の3ステップをしっかり押さえることが、構成成功の第一歩です。
ナビゲーションの設計
サイトの構成が固まったら、次はナビゲーション(メニュー)の設計です。ヘッダーのナビゲーション(メニュー)設計をすることで、ユーザーの迷子防止につながります。必要な情報にすぐアクセスできるよう、階層を浅く、ラベル(文言)は分かりやすく明快にするのが基本です。
たとえば、「WORKS」や「CONTACT」など英語表記を使いたくなる場合もありますが、見た目はおしゃれでもユーザーにとって分かりづらいことがあります。特に建築業界のターゲット層では、日本語で直感的に伝えることの方が効果的です。
また、施工事例や料金、問い合わせなど、ユーザーの関心が高い項目はトップメニューに配置しましょう。ナビゲーションが整っていることで、ユーザーの離脱を防ぎ、成果につながるサイトになります。
ページ単位での構成を設計する
ホームページ全体の構成が整理できたら、次は各ページごとのページ構成設計に移ります。トップページやサービス紹介、施工事例、会社概要、問い合わせページなど、ページごとに役割や目的が異なるため、それぞれに応じた情報の整理と設計が必要です。
たとえば、トップページでは会社の強みを端的に伝え、サービスページでは具体的な提供内容や対応エリア、料金の目安を提示するといった具合に、「そのページに訪れたユーザーがどんな情報を求めているか」を想像してページ構成を考えることがポイントです。
単にページに情報を詰め込むのではなく、ユーザーの行動を自然に促す流れ(ストーリー)を意識することが成果につながるページ構成の鍵になります。
各ページの要素とデザイン
各ページには、それぞれにふさわしい情報要素と配置があります。たとえばトップページには、以下のような情報を明快に整理して配置するのが効果的です。
- 会社の特徴や理念(ファーストビューや冒頭)
- 提供サービスの概要(ビジュアルで直感的に)
- 最新の施工事例やお知らせ
- お客様の声・実績紹介
- 問い合わせや資料請求への導線(CTA)
一方、下層ページ(例:サービス紹介ページ、施工事例ページ)では、詳細な内容と信頼性を伝える情報を丁寧に掲載したほうがいいでしょう。さらに、CTA(問い合わせ・資料請求ボタンなど)は視線の流れや読了タイミングに合わせて、適切な位置に設置することが重要です。たとえばファーストビューとページ末尾の両方にCTAボタンを配置することで、読み手の行動を逃さずにキャッチできるのでおすすめです。
どんな見た目にするかを最初に考えるのではなく、どんな文言をどこにどんな流れで載せるのか、どんな順番で情報を配置するかを考えましょう。
ワイヤーフレームの役割
ページ単位の構成を検討する際に欠かせないのが、「ワイヤーフレーム」の作成です。ワイヤーフレームとは、ページのレイアウトや情報の配置を視覚的に整理した設計図であり、画像や色などのビジュアル要素を加える前の“骨組み”にあたります。
この段階では、「見出しの位置はどこか」「問い合わせ導線はどのように設けるか」「ユーザーはどの順に情報を読むのか」といった情報の流れや優先順位を明確にすることが目的です。
デザインに入る前にしっかりとワイヤーフレームを設計しておくことで、制作過程での認識違いや手戻りを防ぎ、スムーズな制作進行と成果につながるサイトづくりが可能になります。
ワイヤーフレーム作成の手順
ここでは、成果につながるワイヤーフレームを作るための手順を3つのステップに分けてご紹介します。
ワイヤーフレーム作成の手順①必要情報の洗い出し
まずは、そのページに載せるべき情報をすべて洗い出すことから始めます。ページの目的に応じて、どんな内容が必要かを整理することで、情報の抜け漏れを防ぎます。競合サイトの構成を参考にしながら、自社に合ったページ構成を洗い出し検討するのも効果的です。
たとえば、サービス紹介ページであれば
- サービス名と概要
- 対応エリア
- 他社との違い(強み)
- 料金の目安
- 施工の流れ
- お客様の声
- よくある質問(FAQ)
- CTA(問い合わせ・資料請求ボタン)
などが挙げられます。この段階では、情報を文章として書き起こす必要はありません。「何を伝えるか」という情報単位で洗い出すことがポイントです。
ワイヤーフレーム作成の手順②コンテンツの優先順位付け
洗い出した情報をもとに、ユーザーがどの順番で情報に触れるべきかを考え、優先順位をつけていきます。訪問者はページを上から下へとスクロールして閲覧するため、特にスマートフォンの場合、最初に表示される情報(ファーストビュー)は非常に重要です。
ファーストビューには、ユーザーの関心を引く要素、つまり「このページには自分の求める情報がある」と思わせる見出しやキャッチコピーを配置しましょう。会社のイメージが一瞬で伝わる写真やキャッチコピーの配置が鍵となります。
その後、ユーザーの疑問や不安に応えるような情報を順序立てて配置していき、最終的には「問い合わせしたくなる状態」に導く流れをつくるのが理想です。
ワイヤーフレーム作成の手順③レイアウトの決定と配置
最後に、優先順位を反映した情報の配置・レイアウトを決めていきます。ワイヤーフレームでは、以下のような構成要素をブロック単位で配置していきます。
- 見出し(H2、H3など)
- テキストブロック
- 画像スペース
- CTAボタン
- お客様の声・実績
- よくある質問などのアコーディオンメニュー
この段階で色やフォントはまだ必要ありません。あくまで「どこに何を配置するか」「情報がどんな順序で並ぶか」を可視化することが目的です。レイアウト設計では、ユーザーの視線の動きや読了タイミングを意識し、「読みやすい」「理解しやすい」「行動しやすい」ページ構造をつくることが求められます。
リフォーム会社に特化したウェブ集客支援サービスのページはこちら
定期的な見直しと更新の重要性
ホームページの構成は、「一度作って終わり」ではありません。時代の流れやユーザーの行動、競合他社の動向、そして自社のサービス内容など、ビジネスを取り巻く環境は日々変化しています。
たとえば、スマートフォンの普及によって「ファーストビューの設計」が重視されるようになったり、Googleの検索アルゴリズムが変わることで「重要視されるコンテンツ」が移り変わったりと、構成に求められる要素も常にアップデートが必要です。特に建築業界では、以下のようなケースで構成の見直しが必要になります。
- 取り扱う商品ラインナップやサービス内容が変わった
- ターゲットの年齢層や属性に変化があった
- SEO順位が落ちた/問い合わせが減った
- 競合がわかりやすい構成で成果を上げている
こうした変化に対応するためには、定期的な構成の棚卸しと調整が不可欠です。サイトリニューアル後、データの結果を活かしホームページを修正し施工事例ページの閲覧数が2倍に増えたという企業もあります。
市場やユーザーの変化への対応
ユーザーのニーズや検索行動は、数カ月〜1年単位で変化していきます。たとえば、「補助金対応リフォーム」が話題になれば、その情報を求めてサイトを訪れる人も増えます。そうしたトレンドに合わせた情報設計ができていなければ、せっかくのアクセスを逃してしまうことにもなりかねません。
また、以前は有効だった構成が、時間とともに陳腐化することもあります。たとえば「施工事例がPDFでしか見られない」「スマホで見づらい」「CTAがわかりにくい」など、ユーザー体験が損なわれている可能性があるのです。
そのために有効なのが、アクセス解析ツール(Google Analyticsなど)やヒートマップ(Scrollmap、Clickmap)を使った検証です。これらのツールをホームページ公開後に活用する方法が効果的です。
- どのページがよく見られているか
- 離脱率が高いページはどこか
- CTAまでスクロールされているか
こうしたデータをもとに、構成のどこを改善すべきか、どの情報が過不足なのかを客観的に判断できます。「どのページで離脱しているか」「クリックされていないボタンはないか」など、具体的な課題を洗い出すことで、構成改善の方向性が見えてきます。
また、社内で新しいサービスを始めた際や、問い合わせ内容に変化が見られたときにも、それに合わせて構成や導線の再設計を検討することが重要です。ホームページは“作りっぱなし”ではなく、事業とともに進化させるべき資産です。構成のアップデートは、成果を継続的に生み出すための投資と考えましょう。
さらに、ユーザーインタビューやアンケートを通じて「実際の声」を取り入れることで、机上では見えない改善点にも気づけるでしょう。
ホームページは“育てる”もの
ホームページは「作ったら終わり」ではなく、公開後に改善と検証を重ねることで成果を最大化する“育てる媒体”です。特に構成は、ユーザーの使いやすさ・回遊性・SEOすべてに直結するため、アップデートの優先順位も高くなります。定期的に構成を見直すことで、競争力を維持しながら成果につながるホームページを保ち続けることが可能になります。
まとめ
建築会社のホームページは、魅力的なデザインだけでなく、成果につながる「構成」があってこそ機能します。ユーザー視点を大切に、シンプルで分かりやすく、かつ柔軟に改善できる構成を目指しましょう。適切なサイト構成は、問い合わせ・資料請求の増加に直結する「資産」になります。
私たちゴッタライドでは、建築会社・リフォーム会社・塗装会社など、住宅業界に特化したホームページ制作・改善支援を行っています。構成設計からワイヤーフレーム作成、SEO対策まで、一貫してお手伝い可能です。「今のホームページを見直したい」「これから作りたいけど何から始めれば?」という方は、ぜひ一度ご相談ください。無料相談会を実施中です。あなたのホームページが、ただの名刺代わりではなく、反響を生み出す営業ツールになるよう、私たちがしっかりサポートします。



 資料ダウンロード
資料ダウンロード お問い合わせ
お問い合わせ